読み応えあり、西部劇研究書 ― 2016/02/27
『捜索者ー西部劇の金字塔とアメリカ神話の創生』グレン・フランクル著(新潮社)の書評が日経新聞に載ったのは、去年の10月だ。切り抜いてファイルに入れ、本を図書館にリクエストした。順番が来るまでに『捜索者』(1956年)その他の西部劇映画を何本か見た。『駅馬車』『アパッチ砦』『黄色いリボン』『シェーン』『大いなる西部』『明日に向かって撃て』『デッドマン』など。ネイティヴ・アメリカンが映画ではどう描かれているのか、漠然とした興味はあったもののとりとめなく西部劇を見た。
2月中旬ようやく本が回ってきた。500ページを超す大作だ。まずコマンチ族に拉致されたシンシア・アン・パーカーとその息子クアナ・パーカーについての史実が語られ、アラン・ルメイの小説に繋がる。そしてジョン・フオード監督とジョン・ウェインなどの、映画製作にまつわる様々な挿話が続いてゆく。アメリカ開拓とは、凄まじい殺戮と暴力と人種差別の歴史だったのだ。その渦の中に否も応もなく置かれた人々が、懸命にそれぞれの人生を生きていく。奥行きのある内容に圧倒された。
楽しい話をふたつ。
1、
フォード監督はモニュメント・ヴァレーでの撮影を通してナヴァホ族を支援したのだが、撮影時には祈祷師ホスティーン(愛称デブおやじ)に天気を頼んでいた。ウィスキーを一杯飲ませてから翌日の希望を伝えると、謝礼15ドルでいつも芝居向きの天気が用意されたという。例えば青い空にふわふわ雲を3つばかり浮かべるとか。
2、
『捜索者』はイギリスでも上映され人気を博した。ジョン・ウェイン(イーサン)のセリフ"That'll be the day"(ありえない/まさか)は1957年バディ・ホリーの曲になり、それを初レコーディングのA面にしたのがリバプールのロックンロール・グループThe Quarry Menだった。ザ・クオリーメンのメンバーから、数年後ザ・ビートルズが結成された。
手元に子供向けFandexのこんなカードがある。確か2012年のクリスマスに雪で入場できなかったメサ・ヴェルデかアズテク遺跡の売店で買ったもので、インディアンの部族ごとに説明が書かれている。情け容赦のない馬使いコマンチ族のカードには、酋長クアナ・パーカーの写真が載っていた。本を読むまで気づかなかったけど。

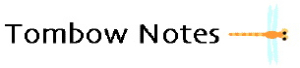




最近のコメント