10月のセゴヴィア、アヴィラ、トレド ― 2025/12/04
マドリードからの小旅行は(各1日)
1、セゴヴィア&アヴィラの現地バスツアー
2、電車でトレドへ、旧市街の散策
どこも以前から興味のあった場所だ。写真を少し置いて、備忘録としよう。
ローマの水道橋はSegoviaの町の入り口にある。すごいですね、古代ローマ人。
セゴヴィアの大聖堂

セゴヴィア名物は、Botinで食べられなかった子豚の丸焼き(コチニージョ・アサード)ね。

アヴィラの城壁
スペイン国鉄 Renfe でトレドへ。
駅からどんどん歩く。テージョ川にかかるアルカンタラ橋を渡る。
そこからは過酷な坂道が待っていた。

サンタ・クルス美術館

トレイン・ヴィジョンで町を一回り。

これを観るため

ほらね!
どこかの広場に続く階段。
その先に迷路のような細い道(高低差あり)が続いていた。

サント・トメ教会のエルグレコ
エル・グレコ美術館のトレド風景
トレド名物のマジパンとコーヒーでひと休み

さようなら、トレド。この日は12km歩き、22階分の階段と坂道を登った。
もう限界です。

帰りのレンフェ。高速列車Avantなら、マドリードのアトーチャ駅までほんの40分足らずで着いてしまう。

10月のマドリード美術散歩 ― 2025/12/04
ダブリン4泊後、マドリードに移動した。ドイツに戻るCさん夫妻は、前日の夕方
「次はどこに行きましょうか」と言っていた。
去年のナポリもダブリンも楽しかったし、都合が合えばまた集合できそうだ。
マドリードではこんなAirbnbに6泊した。小さなキッチン、冷蔵庫、エアコン、Wifi、トイレ&シャワールーム付き。アトーチャ駅から徒歩数分、そして何とすぐ裏手がソフィア王妃芸術センターなのだ。

でも、到着日はソフィア王妃が休館だったため、まずは プラド美術館 へ行くことにした。
入り口に続く長蛇の列は何?と尋ねると、終了2時間前からは無料になるのだそうだ。それならと、30分ほど並んで入場することにした。

ラス・メニーナス の前も、ボスの 快楽の園 の周りも人で溢れかえっている。この美術館は撮影禁止だ。ゴヤ、エル・グレコ、ラファエロ、カラヴァッジョ、ルーベンス、レンブラント、ブリューゲル、、、オーディオガイドを聴きながら彷徨い、歩き疲れたけれど物足りない。もう一度来るとしよう。
グルメツアーではない。ブランドショッピング・ツアーではない。絵を観にきたのだ。美術館近くの生ハム博物館(という名前の店)で質素な晩ご飯を取り、カルフールに立ち寄って翌日の朝食他を買い込みAirbnbに戻った。

2日目の朝、ソフィア王妃芸術センター の開館を待つ。

マドリードに行ったのは、ちょっと大げさだが、人生3度目の、恐らく最後のゲルニカを観るためだった
1978年にNYCのMOMAで、2007年にここで観て、確か旅記録も書いている。18年前は撮影禁止だったが、いつからか撮影自由になったらしく、大勢がスマホを向けていた。あれからナショナル・グラフィック制作の『ジーニアス・ピカソ』(アントニオ・バンデラス主演)があり、バンクーバーで画期的な「ピカソと女性たち」展に行った。バルセロナのピカソ美術館でラス・メニーナス・パロディ集に笑い、MOMAでキュビスムの出発点とされる「アヴィニョンの娘たち」も観た。日本の関連展覧会にも何回か足を運んでいる。けれど、ゲルニカは格別だ。圧倒的な力の前に、しばらく立ち続けた。
数多くある「泣く女」のモデル(当時の恋人)ドラ・マールが記録したゲルニカ制作過程の写真が、後ろの壁に掛けられていた。これは「ハンカチを持つ泣く女」

その後「ヘミングウェイが食事した」Botin (世界最古のレストラン)に足を伸ばしたが、以前とは大違い。年内は予約で一杯だと門前払いになり、仕方なく数件先の店で遅いランチを取った。美味しいパエーリャだけど、食べ切れません。一人旅の困った点はこれね。半分お持ち帰り。マヨール広場周辺を回ってジェラートでひと休みし、AirBに戻った。

翌日、プラドの少し先にある ティッセン=ボルネミッサ美術館 に行った。ここがまた素晴らしい、のだけど、そう、訪問の翌週から現在も「ウォーホル&ポロック展」を開催中なのだ。残念、少し日程がずれていればねえ。

鉄鋼業で成功をおさめたハインリッヒ・ティッセン=ボルネミッサ男爵の美術コレクションは、プラドとソフィア王妃を補足するようなものになったようだ。中世の作品もあったが、特に印象派以降や20世紀美術が充実している。
ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌ、青騎士派、エゴン・シーレやドイツ絵画もあり。E.ホッパーやオキーフ、ワイエス、リヒテンシュタインなどのアメリカ美術に驚いた。
どこにいても静かなホッパー

珍しく鮮やかなオキーフ

海外の美術館では、よくこんなふうに校外学習中の先生と生徒たちを見かける。

must-go のサン・ミゲル市場に足を伸ばした。

にぎやか、美味しい。シーフード・フライとビールを楽しんでから、ピンチョス数種を持ち帰った。

もう一つの must-go は日曜のフリーマーケット、エル・ラストロ蚤の市だ。
他と比べられない大きな規模で、無数の店が軒を並べている。面白すぎて、丸一日いてもよかったのだけど、考古学博物館に割ける時間はその日の午後しかない。

地下鉄を乗り継ぎ、急いで 国立考古学博物館 へ。
歴史的遺物だけでなくデジタル展示物が素晴らしい。アルタミラの壁画がその年代や地図とともに映像で見られる。こうしたデジタル資料はアテネでもイスタンブールでも国立博物館に置かれていたのに、なぜ日本では作らないのだろう。上野の国立博物館(今年も外国人学生を案内した)は少々退屈なのでは?

古代イベリアの彫刻エルチェの貴婦人(BC4ー5世紀)
古代ローマに支配される前の謎に満ちた(未だ解明されていない)文化らしい。

最終日、エティハド便の出発は夜だったので、スーツケースをAirBに預け、再びプラド美術館に行った。初日はふわふわ興奮していたけれど、この日は落ち着いて迷子にならず、名画と向き合って3時間余りを過ごした。
よい旅行だった。
最後の川村記念美術館 ― 2025/03/15
何回かの訪問で最も印象に残っているのは、階段を上がると広がる明るい部屋に架けられたバーネット・ニューマンの大作「アンナの光」だ(縦276cm 横611cm)。
2013年に売却されて、もう見ることはできない。探してみたら、紋谷幹雄さんという方のサイトに画像を見つけましたので、お借りします。https://monyaart.jugem.jp/?eid=3570

はじめてこの絵と向かい合った時、静かに座っている係の女性に
「1日中、これを見ているんですね。何を考えますか」と尋ねると
「アンナというのはバーネット・ニューマンのお母さんです。
わたしも母を亡くしているので、いろいろ思い出しています」
というお返事をいただいたことを思い出す。
2011年にはヘンリー・ムーアのある広場に、4種類のひまわりが植えられていたことも印象深い。
ゴッホ、ゴーギャン、マチス、モネのひまわりが咲き誇る!と聞いて、夏の初めに行ってみたら、ゴッホのひまわりがひとつだけぽつんと、背を伸ばして咲いていたっけ。

やっぱりもう一度行かなきゃ、と車を走らせたのは3月初旬の冷たい雨の日だった。閉館間近の美術館は、悪天候にも関わらず人が多かった。ざわざわしたロスコの部屋に座って、今まで通りしばらく時間を過ごした。美術館前の池では白鳥が2羽、噴水の先の岸辺でじっと動かなかった。さよなら、さよなら、もう来ないの。
六本木に新設される美術館にもRothko Roomができるというニュースはうれしいけれど、何と作品の3/4は売却されてしまうらしい。シャガール「ダビデ王の夢」やカンディンスキー、エルンスト、ポロックにまた会えるといいんだけど。
元気ないけどシアトル(第20次遠征隊#5) ― 2024/10/05
めったにないことだが、フェアバンクス3日目に体調を崩した。嘔吐、発熱、咳、喉の痛み、、旅行人格の空元気も役に立たない。Mが世話してくれたおかげで熱は引いたものの、全く食欲がない。そういう状態の帰り道シアトルだ。楽しいはずのfish toss魚投げパイクプレースも、少し歩けば疲れてしまう。スタバ1号店前の大行列を横目に通り過ぎ、有名チャウダー店に入ったがほとんど味がしなかった。
「ゴールド!ゴールド!ゴールド!」
壁に拡大展示されていたのは、1897年7月蒸気船ポートランド号が2トンの金と68人の大金持ちを乗せてシアトル港に到着した日の新聞見出しだ。富を求める何万人もの人々が、我も我もと北へ向かうことになった。
小さな港町シアトルはそのようにして、19世紀末、金探求者たちが様々な装備品を整える拠点となり急速に発展したという。防寒衣類、頑丈な靴、猟銃、ツルハシ、鍋、小麦粉、ベーコン、砂糖、タバコなどなど、(現在パイオニアスクエアと呼ばれている)商店街の歩道に商品の山がうず高く築かれた。ゴールドラッシュ特需である。解説展示の中に若いジャック・ロンドンの写真を見つけた。

もうひとつのmust-see、シアトル美術館で楽しみにしていたのは、アフリカンアメリカンの画家ジェイコブ・ローレンスの小さな展覧会だった。ハーレム・ルネサンスに学んだ彼の作品は、ひと目見れば印象に残る独特の深い色合いだ。
そしてやはり、ネイティヴ・アートの前でも足が止まる。
Raven 大鴉、ワタリガラス、、ハイダ族では創造性creativityのシンボルとされている。

最終日の夕方、エリオット湾を1時間で小さく一周するクルーズ船に乗った。初秋の風が心地よい。けれど、うつしてしまったのか(ごめんね)旅仲間Mも風邪をひいている。ゴホンゴホンと咳き込む二人。ドラッグストアWalgreensウォルグリーンズで買ったTylenolタイレノールの風邪薬を分け合い帰国した。お疲れさま〜
秋の中欧旅行①ベルリン ― 2023/10/20
ここ何年か、次はどこへ旅行したいの?
と聞かれるたびに、んー、ベルリンかな、と答えていた。実際のところコロナ後に行ったのは別の場所だったけれど、さあそろそろ出かけなくてはね。
9月15日からの中欧一人旅(16泊18日)備忘録です。
成田からトルコ航空利用、つまりイスタンブール経由で到着は夜11時過ぎ。
遅延のため、ホテルの最寄駅までの直通電車は終了していた。直通電車があるから選んだホテルなのに、、。
初めて利用するSバーンとUバーン、チケット購入も手間取る。が、幸い、同じ方向へ行く親切な女の子18歳が乗り換えまでを手伝ってくれた。長すぎて言いにくいゲズントブルンネン駅に着く。暗い駅前道路をできるだけさっさと歩き、静まり返ったホテルにチェックインした。
初ベルリンは4泊(観光は正味3日間)だ。 青字リンクしてます。
<観光1日目>
まずはここへ行くのだ。
過去の様々な時代の絵や映像や写真を、これまでに数多く見た。ナポレオン、ナチスの旗、前を遮るベルリンの壁、そして壁の崩壊、、
感慨にふけりながら広場を歩き、クアドリガと女神を見上げ、門をゆっくり正面からくぐり抜けた。(と、この日は平穏だったが、翌日夕方ここを通った時には、環境団体による抗議の塗料吹きつけ事件が起きていた。)
見渡す限りに2,700余りの石碑が並んでいる。

西の公園を斜めに通り抜け、絵画館 Gemäldegalerie と現代美術館 Neue Nationalgalerie を回った。
レンブラント、ホルバイン、フェルメール、カラヴァッジオ、そしてキルヒナー、ベックマン、、
初日の午前中そんなに急いでどうする?と自問しつつも、気が急いてしまう。
ベルリンは美術都市でもあるのだ。オンラインで入手しておいたミュージアムパス Museum Pass Berlin の有効期限は3日間、30ヶ所もある博物館/美術館のうち、一体いくつ訪ねられるだろうか。走り回らずゆっくりと作品を観たい、でも気持ちは前のめりになっていく。
気がつけば、午後2時を過ぎている。
ヴィム・ヴェンダース 『ベルリン・天使の詩』 の頃とは全く違うポツダム広場を抜け、モール・オブ・ベルリンのフードコートで名物カリーヴルストを注文した。ふーん、これなのか。

そして、テロのトポグラフィ Dokumentationszentrum Topographie des Terrors

さらに、冷戦時代の境界線を象徴するチェックポイント・チャーリー Checkpoint Charlie へ。
大勢の観光客が交代で写真を撮っていた。

既に夕方だ。
この日行った場所はどれもブランデンブル門から南北/東西2、3kmの範囲にあるのだが、美術館内の歩行を入れればかなりの距離を歩いたことになる。疲れてきた。
土曜日のうちにホテル近くの大きなスーパーで水などを買う必要もあり(翌日曜は休み)、ようやく分かりかけてきた地下鉄Uバーンで戻ることにした。
<観光2日目>
博物館島へ行く。これはヴェンダースの2作目にも出てきた旧国立美術館 Alte Nationalgalerie だ。さびれていた映画の場面とは違い、入館者の列までできていた。クリムトの展覧会が開かれていたからだ。

博物館島には5つの大きな国立博物館がある。1日で全部回るなんてとんでもない。
バビロンのイシュタール門、何という美しさだろう。ペルガモンの大祭壇は改修工事中だ。そしてこの10月23日から、博物館全体がしばらく休館になるという(ダスパノラマは公開)。
ペルガモンから新博物館 Neues Museum に移動した。
有名なネフェルティティの胸像、この周囲だけは写真撮影が禁止されている。膨大な数の所蔵品に、頭がクラクラしてきた。

旧国立美術館で主に常設作品を観て(実はなぜかクリムトが苦手なのだ。ウィーン世紀末ならエゴン・シーレとココシュカのほうが好き)、博物館島入り口のジェイムズ・サイモン・ギャラリー2階のカフェで遅いランチをとった。
それから橋を渡り、川沿いで行われている週末のフリーマーケットをぶらぶら歩いてから、ドイツ歴史博物館へ行った。が、本館は工事中のため休館中だ。イオ・ミン・ペイ設計のガラス新館で(1989年のベルリンの壁崩壊を起点に過去へ遡る)ROADS NOT TAKEN という企画展と、全く知らなかったドイツのシンガーソング・ライター Wolf Biermann 展を見た。薄っぺらだった自分のベルリン観に、ほんのわずか厚みが加わったような気がする。
この日と翌日は、バス地下鉄トラム共通の1日チケット(現在€9.50)を利用した。目抜通りウンター・デンリンデンの国立歌劇場前からバスに乗り、(無料だが)時間予約済みの国会議事堂へ向かった。
<観光3日目>
must-seeはイーストサイド・ギャラリーだ。ベルリンの壁 Berliner Mauer は部分的に保全され、シュプレー川沿いの壁には100以上のグラフィティが描かれている。
最も有名な独裁者のキス(ブレジネフとホーネッカー)前には人だかりができており、観光ボランティアが気づかないうちにこんな新聞を作って手渡してくれた。

白水社の『若きWの新たな悩み』を読んだのは70年代、東西冷戦の頃だった。ライ麦畑的Wの悩みは、記憶が正しければ、USA製のジーンズをいかに入手するか、なのだった。
映画『グッバイ・レーニン』はしばらく前に、旅行を決めてから『善き人のためのソナタ』とヴェンダース2作品を見た。戦争関連の映画や映像の世紀なども。
肩の上につい天使カシェルを探してしまう戦勝記念塔 Tiergarten。バスはぐるりと円柱を回って南へ進んだ。

カイザー・ヴィルヘルム記念教会 Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche の前でバスを降りる。1943年イギリス軍によるベルリン大空襲で、大きく破壊された教会だ。その横の新教会の壁は、2万枚以上の青いガラスで作られている。心落ち着く静かな空間だ。


ジグザグ鋭角の複雑な建物の中に、印象深い展示物が収められている。急な階段を上り下りし角を曲がりながら、ユダヤ人の経た困難な時代を辿っていく。顔のように見える丸い鉄片をザクザクガシャガシャと踏んで歩くこの空間では、誰もが沈黙してしまう。

それからアレクサンダー・プラッツまでトラムに乗り、Uバーンでゲズントブルンネン駅に戻った。慣れた頃には次の目的地へと移動なのだ。

NYCの4日間(第19次遠征隊#6) ― 2023/06/19
旅の備忘録。
ボストンのサウスステーションからAmtrak特急で3時間半、ニューヨークのペン・ステーションに着いた。拡張されたモイニハン・トレイン・ホールは、高い天井から差し込む午後の光が明るい。
それから4泊。NYCでしたことをざっと列記しておこう。
宿泊場所:マンハッタンのAirbnb、
とても広々とした部屋で、中庭もある
オーナーは日本人写真家
行った場所、主に:
ダコタハウスとセントラルパーク
メット(メトロポリタン美術館)
MOMA(ニューヨーク近代美術館)
ブロードウェイ・ミュージカル アラジン
ジャズクラブ バードランド




タイムズスクエア、スーパーTrader Joe'sやWhole Foods、毎回足を運ぶ古書店 Strand Book Store、インド料理店、トルコ料理店、ハンバーガー店、地下鉄、道端のお店あれこれ、、4日間のできごとは既にグルグル絵巻ものみたいになっている。
ほぐしてみると、ギャラリーを見に行って迷子になったMや、買い物止まらない娘、夕暮れのクライスラービルをカメラに収めるYさん、メットでようやく見ることができたFLライトの部屋、バードランド前で一緒に写真を撮ったビッグチーフの顔などが次々に浮かんでくる。
2008年と11年には、一人で市内を走り回ったものだ。テディ・ルーズベルトの生家、ボブ・ディランがグリニッチ・ビレッジで初めて歌った店、ガートルード・スタインの像、、、そうした過去の文学的ランドマーク巡りも楽しかったが、4人で歩いた今回の旅行はより思い出深いものになりそうだ。
ボストン名所巡り(第19次遠征隊#5) ― 2023/06/18
ボストン最終日はどこへ?
外せない場所が多いけれど、ボストン美術館 とハーバード大学周辺へ行ってみようか。
ボストン美術館では北斎展が開催中だった。
4人でまずゴーギャンのマスターピースまで行き、解散。2時間半後にミュージアム・ショップで待ち合わせた。楽しい。でも、名画を観過ぎて頭がガチガチだ。

ハーバード・スクエアまで移動し、クラム・チャウダー&ロブスターロールのランチ。
大学生協へ立ち寄ってから大学構内を散歩した。
図書館の石段に座り、もちろんジョン・ハーバード氏のピカピカ靴にタッチする。


それからボストン・コモンへ。
日曜日の夕方だ。ビーコンヒルのおしゃれな店はそろそろ閉まり始めているだろう。何ブロックか先にあるアフリカン・アメリカン歴史協会は、たぶん休館日だ。パブリックガーデンの「かもさんおとおり」も見たいが、少し遠過ぎる。一日にできることって少ないよね。
というわけで、
17世紀に建設されたアメリカ最古の歴史ある公園を4人はゆっくり歩き、ベンチに座り、散歩中の犬を眺め、近くのメキシカン・レストランで夕食を取ってbnbに帰った。
翌日は移動日だ。

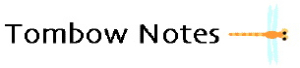















最近のコメント