フェルメールの帽子 ― 2014/06/17
帽子というキーワードが、ティモシー・ブルック著『フェルメールの帽子』(岩波書店)につながった。何という面白さだろう。
「デルフトの眺望」が東インド会社へ、「兵士と笑う女」の兵士の帽子がカナダ、セントローレンス川の毛皮貿易へと展開していく。その跳躍ぶりは、陳腐な言い回しだが「時空を超えた知的冒険」そのものだ。ははー、先生、参りました。
ブリティッシュ・コロンビア大学のティモシー・ブルック教授は、中国史がご専門のようだ。研究書が何冊も出版されているが、『フェルメールの帽子』は「作品から読み解くグローバル化の夜明け」という副題の通り、画家研究や作品論や美術史論ではない。フェルメール作品を仔細に眺める視線がヨーロッパからカナダ、中国へと広がり、17世紀の世界そのものを論じる。本は高い評価を受け、2009年にコロンビア大学の歴史賞を受賞した。
発端はブルック教授が青年の頃のオランダ旅行だという。サイクリングで道路脇に転び、一晩お世話になった家で偶然目にした絵葉書への興味が、40年後、この壮大な物語として結実した。
帽子は第二章、
「フェルメールが、帽子を複数持っていたのは間違いない。こんなことに言及した文書はひとつもないが、彼と同世代の社会的地位のあるオランダ人で、帽子をかぶらずに人前に出る者など一人もいなかった。」
フランス人毛皮商人、モホーク族、火縄銃、ワムパム(米国務省Eジャーナル、イロコイ連邦wiki、拙旅行記)、ビーバーの毛皮、ヒューロン連盟、、、わたしがずっと追いかけているアメリカ先住民のテーマが、兵士の派手な帽子に結びつく。これぞ、読書の醍醐味ですねえ。
Asian Art Museum(サンフランシスコ)が 、iTunesUにブルック先生の講演を置いている。timothy brook vermeerで、"The Coins on Vermeer Table"(本では第三章と第六章の内容)を検索できるはずだ。
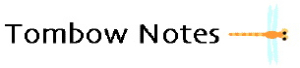




最近のコメント