ハドソン湾クエスト#3 ― 2016/05/13
エピソード2 湖
初日の水漏れなど、ほんのささいなトラブルに過ぎなかったことを知る。ウィニペグ湖の南北の長さは416km。風に押し戻されながら、一日に10時間以上北へ北へと漕いで行く。真夏の暑さもさることながら、一行を最も苦しめたのは絶えず襲いかかる虫だった。体の周りを飛び回り四六時中耳元でブンブンうなり、全員が睡眠不足になった。どうやって眠るかが大きな課題になり、積み荷を覆う布を縫い合わせテントに仕立てた。頭に袋をかぶり「エレファントマン」になった者もいた。川沿いの知り合いの家でもらったジャムや蜂蜜が元気を奮いたたせ、ミシシッピ川を行くトム・ソーヤの気分にもなった。そんな時、旅は達成可能 attainable のように思われた。
17日目、食料にカビが生え始めた。多く積まれていた保存食ペミカンまでも。バッファロー、鹿、エルクとムース(ヘラジカ)などの肉と脂肪にブルーベリーやカラント、木の実などを混ぜ込んで作られるペミカンは、元々ネイティヴ・アメリカンの食べ物だった。度重なる水漏れで積み荷はすっかり湿っている。
19日目、湖北端にあるクレー族の Norway House ノルウェイ・ハウスでは York Day の祭りが行われていた。ハドソン湾会社が中継地として利用した場所だ。バグパイプに歓迎されて上陸し、補給を受けた。スコットランドからの先祖が、150年前にその村を通り過ぎたのだ。
エピソード3 グレイト・ポーテージ
数世代前の traders たちが大勢 Norway House の川を見下ろす墓に眠っている。たやすい旅路ではないことをひしひしと感じ、ネルソン川を東へ漕ぎ進む。Sea River Falls シーリバー滝で最初の portage 連水陸路運搬(繋がっていない川と川の間の陸路を船を引いて移動すること、つまり、まず積み荷を何度も背負って運んだ後、大きく重いヨーク船を次の川まで引いていく)を経験、木の生い茂る凸凹の小道40mを抜けるのに24時間かかった。彼らの前にはまだ幾つかの portage が横たわっている。
Echimamish River エチマミシュ川でビーバーダム(の呪い)に手こずりながら、さらに東へ進む。29日目、最大の難関(のひとつ) Robinson Portage ロビンソン・ポーテージに到達した。長さは350m。暑さと虫と土砂降りの雨に消耗し、脱落寸前の者も現れた。話し合いの末TV制作会社に援助を求めたが、1840年に助けはあったか?というそっけない答えが返ってきただけだった。ちょうど半分まで来たのだ。前へ進むしかない。
限界まで力を振りしぼり、七日間でその関門を通り抜けた。喜びに湧いて再び水の上へ。先祖と同じ時間をかけてグレイト・ポーテージを通過した彼らは、苦痛はいつか過ぎ去り美しさが残るという教訓を得ただろうか。
ハドソン湾クエスト#2 ― 2016/05/08
エピソード1 冒険の仲間
500人を超える応募者の中から厳しい体力/心理テストを経て8人が選ばれた。報酬は各1万ドル。高校の歴史教師、大工、会社員、修士号を持つ院生 Cowie の曽祖父 Isaac はヨーク船の乗組員であり、同じ行程の1867年の日記を書き残している。他は大学生、金融アドバイザー、ツアーガイド、女性編集者。
木製の船は初日に水漏れし修理、初めての帆を揚げる。皆で名前を Hudson と決めたが、じきにBOB(Beautiful Old Boat)と呼ばれるようになった。嵐が近づき、19世紀にはなかったライフ・ジャケットを着る。 voyageurs の旅では鉄拳が方策を決定したが、8人は全員で話し合い合意しながら進むことにした。レッド川からウィニペグ湖に繋がる広い水域で安全な岸が見つからず、深夜まで漕ぎ続ける。
2001年の夏、かつてハドソン湾会社と契約を結んだ fur traders の跡をたどる旅は8週間から12週間の予定だ。
出発の朝の BOB

7月1日はカナダ・デーの祝日だ。見始めて気づいたが、偶然にもこの日わたしはカナダにいた。プリンスエドワード島のシャーロットタウンも晴天で、港の周辺に人々が大勢集まっていたことを覚えている。夜には花火が打ち上げられるのだ。ウィニペグではバグパイプが演奏され、たくさんの人がBOBの出発を見送った。
エピソードのメモは、書きなぐったものが読めれば、5まで続けたいと思う。
ハドソン湾クエスト#1 ― 2016/05/08
全く遠出しない連休にしたこと。
"Quest for the Bay" をAmazonプライムのビデオの中に見つけ、5回シリーズ各50分を二日がかりで見た。Quest ものは他にパイオニア・クエスト、ゴールドラッシュ(クロンダイク)クエストなども制作されたから、これは「ハドソン湾クエスト」とでも訳してみようか。
2週間前に見たディカプリオの『レヴェナント:蘇りし者』は、アメリカ中西部、ダコタ辺りのフロンティアマンの話だった。19世紀前半毛皮会社と契約を結び、先住民との戦いを避けながら fur trader 交易者たちをガイドした。西部開拓時代に先住民に解け込んで猟師として暮した主人公のような人々は、マウンテンマンと呼ばれたらしい。
「ハドソン湾クエスト」の fur trader は、ヴォエジャー voyageurs と呼ばれていた。フランス語で「旅行者」を意味するこれら北の交易者たちは、カヌーなどで川を移動し、当時ヨーロッパで人気があったビーバーの毛皮をハドソン湾へ運んだ。有名な Hudson's Bay Company ハドソン湾会社は1670年にイングランドで設立された北米最古の会社で、現在ではカナダ最大の小売業の企業になっている。

もう少し説明を加えると、
"Quest for the Bay"シリーズは、カナダのヒストリーTVが制作、2002年に放映されたドキュメンタリー番組だ。voyageurs がその昔どのように川を下り毛皮を運んだのか、マニトバ州ウィニペグからハドソン湾までの全行程1200km、カナダ中央に広がる荒野の湖と川を、1840年のものを再現した木製のヨーク船(長さ40フィート、約12m)に乗り8人が旅した(うち女性は一人)。船には当時と同じ食料、衣類、道具類、そして毛皮など合計1.5トンを超える積み荷が載せられた。
イーサン・ホークとシェイクスピア&カンパニー書店 ― 2016/03/12
イーサン・ホークが主演した『ビフォア』三部作(リチャード・リンクレイター監督)の二作目『ビフォア・サンセット』で、ジェシー(イーサン・ホーク)がセリーヌ(ジュリー・デルピー)に再会するのは、パリの有名な書店Shakespeare and Company Bookstore(日本語wiki解説)だ。小説家になったジェシーのプロモーション・トーク会に、思いがけずセリーヌが現れる。前作『ビフォア・サンライズ』のウィーンの朝から9年後のことだ。
というシーンのいきさつを、実際に本を出版したイーサン・ホークが今年1月に同書店で行われた現実の朗読会で語っている。
(写真も書店サイトから拝借)

先代の店主ジョージ・ホイットマンに撮影を申し込んだ時、「何だって!映画なんかお断りだ。ハリウッドなんてとんでもない。」とけんもほろろに拒絶されたこと。娘(現店主)を通して許可が下りたこと。
イーサン・ホークの本はまだ入手していない。写真の後ろに並んでいる緑の表紙が多分5作目の"Rules for a Knight"だ。 棚の上部に貼られているのは「ウォルト」ホイットマンだろうか。書棚の左に立つくるくるブロンドの女性が、現店主シルヴィア・ホイットマンのようだ。(ウィットマンという表記も)
ノートルダム寺院が見える場所に建つこの書店は二代目で、初代のシェイクスピア&カンパニーはオデオン座に近い場所にあり一度移転したという。シルヴィア・ビーチが1919年、パリで英語の本を売るために開いた書店は貸し出しも行っており、『移動祝祭日』にはまだ若い無名のヘミングウェイがどんなにこの店を頼りにしていたかが書かれている。また、シルヴィア・ビーチの本『シェイクスピア・アンド・カンパニイ書店』で、魅力的だけれど偏屈なガートルード・スタインとアリス・B・トクラスの二人、ジェイムス・ジョイス『ユリシーズ』初版本刊行にまつわる話なども読むことができる。
iTunesUのWGBH Forum Network Arts and Literatureに収められたA Moveable Feast(移動祝祭日)に関するパネル・ディスカッション(ヘミングウェイの孫にあたるショーンなどが参加)では、研究者たちが現シェイクスピア&カンパニーを観光地的な「テーマパーク」と呼んで苦笑していた。が、一文学ファンとしては、どんな大衆文化メディアを通してでも、作家とその世界を身近に感じられることは嬉しいのだ。
シルヴィア・ビーチが「おっかなびっくり」のヘミングウェイをスタインの家に連れて行った話、スタインに彫刻家のジョー・ディヴィットソンを紹介した話、NYCブライアント公園にあるスタイン像、、、あ、そう言えば、ロビン・ウィリアムズ『いまを生きる』のラストシーンでイーサン・ホークたちが唱えるのは、ウォルト・ホイットマンの "O Captain! My Captain!" だった。
もうひとつ付け加えると、『草の葉』にあるその詩は確か1865年、リンカーン大統領を追悼するために書かれたのだ。
読み応えあり、西部劇研究書 ― 2016/02/27
『捜索者ー西部劇の金字塔とアメリカ神話の創生』グレン・フランクル著(新潮社)の書評が日経新聞に載ったのは、去年の10月だ。切り抜いてファイルに入れ、本を図書館にリクエストした。順番が来るまでに『捜索者』(1956年)その他の西部劇映画を何本か見た。『駅馬車』『アパッチ砦』『黄色いリボン』『シェーン』『大いなる西部』『明日に向かって撃て』『デッドマン』など。ネイティヴ・アメリカンが映画ではどう描かれているのか、漠然とした興味はあったもののとりとめなく西部劇を見た。
2月中旬ようやく本が回ってきた。500ページを超す大作だ。まずコマンチ族に拉致されたシンシア・アン・パーカーとその息子クアナ・パーカーについての史実が語られ、アラン・ルメイの小説に繋がる。そしてジョン・フオード監督とジョン・ウェインなどの、映画製作にまつわる様々な挿話が続いてゆく。アメリカ開拓とは、凄まじい殺戮と暴力と人種差別の歴史だったのだ。その渦の中に否も応もなく置かれた人々が、懸命にそれぞれの人生を生きていく。奥行きのある内容に圧倒された。
楽しい話をふたつ。
1、
フォード監督はモニュメント・ヴァレーでの撮影を通してナヴァホ族を支援したのだが、撮影時には祈祷師ホスティーン(愛称デブおやじ)に天気を頼んでいた。ウィスキーを一杯飲ませてから翌日の希望を伝えると、謝礼15ドルでいつも芝居向きの天気が用意されたという。例えば青い空にふわふわ雲を3つばかり浮かべるとか。
2、
『捜索者』はイギリスでも上映され人気を博した。ジョン・ウェイン(イーサン)のセリフ"That'll be the day"(ありえない/まさか)は1957年バディ・ホリーの曲になり、それを初レコーディングのA面にしたのがリバプールのロックンロール・グループThe Quarry Menだった。ザ・クオリーメンのメンバーから、数年後ザ・ビートルズが結成された。
手元に子供向けFandexのこんなカードがある。確か2012年のクリスマスに雪で入場できなかったメサ・ヴェルデかアズテク遺跡の売店で買ったもので、インディアンの部族ごとに説明が書かれている。情け容赦のない馬使いコマンチ族のカードには、酋長クアナ・パーカーの写真が載っていた。本を読むまで気づかなかったけど。

Amazonで見たり聴いたり ― 2015/11/18
Amazonで音楽配信サービスPrime Music が始まった。
が始まった。
Prime Video の内容を確認して、つまりHuluやNetflixと比較の上10月初旬Amazon Primeに再加入したのだが、こんな料金で見放題聴き放題って正しいこと? サービスを受ける側としてはもちろんありがたいけど。
の内容を確認して、つまりHuluやNetflixと比較の上10月初旬Amazon Primeに再加入したのだが、こんな料金で見放題聴き放題って正しいこと? サービスを受ける側としてはもちろんありがたいけど。
ここ最近は通勤の行き帰りにダウンロードした映画やドラマを見るようになり、読みたい本もあってなかなか忙しい(疲れ目に注意!!)
特にNHK地上波放送で見た吹き替え版"Downton Abbey"には笑ってしまうようなセリフがいくつもあり、字幕版でイギリス的に辛辣なウィットを確認できそうなのがうれしい。アメリカ的ユーモアとはずいぶん違うんだよね。
コックのパットモアが下働きのデイジーに
「辞書でも飲んだのかい」いつになく難しい言葉を使ったので
「邪悪な双子に入れ替わったのかい」指示に従わないので
「ナイル川まで水を飲みに行っていたのかい」ただ遅かったので
などなど英語では何と言っているのかな。
Prime Video
ここ最近は通勤の行き帰りにダウンロードした映画やドラマを見るようになり、読みたい本もあってなかなか忙しい(疲れ目に注意!!)
特にNHK地上波放送で見た吹き替え版"Downton Abbey"には笑ってしまうようなセリフがいくつもあり、字幕版でイギリス的に辛辣なウィットを確認できそうなのがうれしい。アメリカ的ユーモアとはずいぶん違うんだよね。
コックのパットモアが下働きのデイジーに
「辞書でも飲んだのかい」いつになく難しい言葉を使ったので
「邪悪な双子に入れ替わったのかい」指示に従わないので
「ナイル川まで水を飲みに行っていたのかい」ただ遅かったので
などなど英語では何と言っているのかな。
リトルロック中央高校と国立公民権博物館(第14次遠征隊#8) ― 2015/10/03
今回の旅行のもう一つのテーマは公民権運動だった。アーカンソー州を横切るなら、必ずリトルロック・セントラル・ハイスクールへ行かなければと思っていた。

1957年9月の出来事について、今、様々な資料を読むことができる。ビジターセンターで記録フィルムを見てから、Little Rock Nineが怒号に包まれながら登った階段を見上げた。池の周りのベンチには9人の名前が記されている。それから58年。
下校時間になると校舎からは大勢の高校生がぞろぞろ飛び出して、ごく当たり前にスクールバスに乗り込んでいくのだった。
メンフィスの国立公民権博物館は、MLキング牧師が暗殺されたロレイン・モーテルに造られている。2009年春に訪ねたことがあり迷ったが、てるてるMをエルヴィスのグレイスランドに送り、やはり足を運んでみた。

行ってよかった。展示物がすっかり新しくなり充実していただけではなく、見る側も以前より少し理解が深まったように思う。映画 "Selma"公開前に読んだコレッタ夫人の自伝、iTunes Uの"the Road to Civil Rights" bookが受け皿を広げてくれたのだろう。胸が詰まるような気持ちで2時間を過ごした。
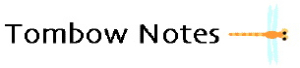




最近のコメント