人工知能時代を考える本 ― 2021/03/15
ハードウェアが自らを設計できる技術的段階、ライフ3.0の時代が近づいた。ほとんどの研究者が、あらゆるタスクで人間を超える汎用人工知能AGIの誕生は今世紀中だろう、と予測している。その後、AGIは人間にコントロールできない速度で進化し、知能爆発シンギュラリティが引き起こされるだろう。未来のシナリオは幅広く、独裁者、征服者、動物園の飼育係、門番、1984、、いずれも好ましいとは言えない。アシモフのロボット三原則から70年、超人的AGIの誕生がもはやSFのテーマではなくなった今、AIが人間の繁栄に役立つよう準備をする必要がある。
というわけで、テグマークが立ち上げたFuture of Life Instituteは、2017年イーロン・マスクやアップル、グーグル、マイクロソフト、大学の代表的なAI研究者たちと共に「友好的なAI」AI安全研究のためのアシロマの原則を策定した。
「友好的なAI」とは、その超知能の目標が人間の目標と合致することだ。つまりAIは人間の目標を理解しなければならない。
「未来の自動運転車にできるだけ早く空港へ行ってくれと頼み、その自動運転車がそれを言葉通りに受け取ったら、あなたは警察のヘリに追いかけられ吐瀉物まみれになってしまうだろう」という極端で愉快な例が語られる。
AIはプログラムを遂行するが、意識と意義を認知するのだろうか?
第8章はサブタイトルの「人工知能時代に人間であること」を「意識」を中心に考察している。とても難しい。ジョン・L・キャシディ作『ケンブリッジ・クインテット』でも議論の要はそれだったと思う。「機械は認知能力において人間と並びうるだろうか」小説の舞台は1949年、コンピュータの父アラン・チューリングに強く反論するのはヴィトゲンシュタインだった。
ところで、エニグマ暗号解読に取り組む映画「イミテーション・ゲーム」に、チューリングがブレッチリー・パークの仲間の労をねぎらいリンゴを配るシーンがあった。アップル・コンピュータのロゴはそこから来たのだという説に、さすがジョブズ!と感心したのだが、どうも本当ではないらしい。むしろニュートンのリンゴやアップル・レコードからというのが正しいようだ。
『LIFE 3.0』に例示された映画は「トランセンデンス」「インターステラー」「スタートレック」「マトリックス」「エクス・マキナ」など。それらはもう遠い未来ではない?
そうそう、未読だけど、関連図書にカズオ・イシグロの『クララとお日さま』を加えなくては。
入門書・参考書 ― 2021/03/01
1月に注文した本がようやく届いた。予想より大判のハードカバーで、カラー図版が美しい。興味のある項目に付箋を貼りながら、日向でページをめくった。
サットン・フーの兜、発掘にまつわる映画があるらしい。Netflix を再開しようか。今日ゴールデングローブ賞を受賞した"Nomadland"も見なきゃいけないし。
冬学期が終了し、時間はたっぷりある。でも、読みたいもの見たいものが多過ぎて、毎日忙しい。
持ち物を増やしたくない年齢になった。たいていの本は図書館にリクエストして読む。でも、図書館にないこんな reference book 参考書類は購入するしかないだろう。Big Ideas Simply Explained シリーズは big idea という書名の通り、物理、経済、宗教、エコロジー、フェミニズムなど大きい分野の概説書だ。しばらく気になっていたが、今回初めて購入した。
読みやすい入門書シリーズは、これまでに幾つも出版されている。1990年代からの Beginner's Documentary Comic Books シリーズはモノクロの愉快なイラストが特徴的だった。絶版もあるが、Kindle版で一部復活した。人文系の難解なテーマが解ったような気分にさせてくれたものだ。



2000年代に入って、2つのシリーズをよく見かけるようになった。
The Complete Idiot's Guide のテーマはポップカルチャー、スポーツ、大学の科目、宗教、料理、クラフト、ライフスタイル、、と多岐にわたっている。ウィットに富んだ語りが楽しかったのに、サイモン&シュスター社からペンギン社グループに変わって少し堅くなったように思う。
Idiot’s Guides Series(リンク)



黄色と青と黒が目を引く For Dummies シリーズは、理系のテーマが中心だった。初期には DOS や Windows の入門書などが並んでいた。畑違いだから一冊も持っていないけれど、リストを眺めると面白い本もありそうだ。
Dummies(リンク)



サットン・フーの兜、発掘にまつわる映画があるらしい。Netflix を再開しようか。今日ゴールデングローブ賞を受賞した"Nomadland"も見なきゃいけないし。
冬学期が終了し、時間はたっぷりある。でも、読みたいもの見たいものが多過ぎて、毎日忙しい。
持ち物を増やしたくない年齢になった。たいていの本は図書館にリクエストして読む。でも、図書館にないこんな reference book 参考書類は購入するしかないだろう。Big Ideas Simply Explained シリーズは big idea という書名の通り、物理、経済、宗教、エコロジー、フェミニズムなど大きい分野の概説書だ。しばらく気になっていたが、今回初めて購入した。
読みやすい入門書シリーズは、これまでに幾つも出版されている。1990年代からの Beginner's Documentary Comic Books シリーズはモノクロの愉快なイラストが特徴的だった。絶版もあるが、Kindle版で一部復活した。人文系の難解なテーマが解ったような気分にさせてくれたものだ。



2000年代に入って、2つのシリーズをよく見かけるようになった。
The Complete Idiot's Guide のテーマはポップカルチャー、スポーツ、大学の科目、宗教、料理、クラフト、ライフスタイル、、と多岐にわたっている。ウィットに富んだ語りが楽しかったのに、サイモン&シュスター社からペンギン社グループに変わって少し堅くなったように思う。
Idiot’s Guides Series(リンク)



黄色と青と黒が目を引く For Dummies シリーズは、理系のテーマが中心だった。初期には DOS や Windows の入門書などが並んでいた。畑違いだから一冊も持っていないけれど、リストを眺めると面白い本もありそうだ。
Dummies(リンク)



二月の教室、二月のベランダ ― 2021/02/05
春が近づいているとは言え、気をゆるめるわけにはいかない。今学期も当然オンライン授業だ。ただし(週1日だけ細々と担当している)Y校の場合、半月に一度登校日が設けられている。学生たちはその日に宿題をまとめて提出し、翌日から使用する配布物一式を受け取り、各課の確認テストを受けるという段取りだ。
昨日が登校日だった。用心、用心。がっちりマスク。緊張しながらJR線に乗った。
けれど、久しぶりにクラスメートと会った学生たちはうれしそう、母国語のおしゃべりが止まりません。お〜い。
確認テスト後「最近の気になる言葉」を各自発表した。ぴえん、ソーシャル・ディスタンス(カタカナ難しいよ、ベトナム語で何?)、三密、ソロキャンプ、、、
Zoom画面では仮面ライダー・アイコンのR君が、「あつ森」の説明をしてくれた。

立春を過ぎたベランダでは、11月に種を蒔いた春菊とほうれん草が今年も柔らかく育っている。ささやかなプランター菜園だが、サラダや青みに少し加えるのにちょうどいい。秋の散歩道からやって来たローズマリーも何とか根付き、小さな新芽が見え始めた。
たったそれだけの二月 ;-)

旅好きな人のために日めくりカレンダー ― 2021/01/05
明けましておめでとうございます。
いつものようでない新年、そのいつもと違う理由が解消されれば、スーツケースを持ってすぐにでも飛び出したい人が大勢いるだろう。
"1,000 Places to See Before You Die"死ぬまでに見たい1000カ所の日めくりカレンダーを買ったのはこれで3度目だ。めくったページはメモ用紙に使えるが、2009年版と2014年版のうち数10枚は、行きたい場所、行った場所に分け、捨てずにクリップ留めしてある。
今年の1月1日ページはマチュピチュだった。上空からの遺跡の写真に「1911年に発見されたインカ帝国の秘境、、」と簡単な英語の説明がある。
日によってはクイズも。翌2日のモロッコ・マラケシュ、イヴ・サンローラン・ミュージアム、彼はコバルトブルーのこの家を1980年代に購入し、2008年に亡くなるまで時折滞在した。さて、サンローランはモロッコ生まれ?正しい/正しくない?(答えは裏面に)という具合だ。
旅に関する引用句が書かれたページもある。
明日はどこだろう?
ページを全部めくり終わるまでに、旅行できますように。
"1,000 Places to See Before You Die"
以前も書いたと思うけど、この本も楽しい。
死ぬまでに見たい1000カ所 ハードカバー第2版
いつものようでない新年、そのいつもと違う理由が解消されれば、スーツケースを持ってすぐにでも飛び出したい人が大勢いるだろう。
"1,000 Places to See Before You Die"死ぬまでに見たい1000カ所の日めくりカレンダーを買ったのはこれで3度目だ。めくったページはメモ用紙に使えるが、2009年版と2014年版のうち数10枚は、行きたい場所、行った場所に分け、捨てずにクリップ留めしてある。
今年の1月1日ページはマチュピチュだった。上空からの遺跡の写真に「1911年に発見されたインカ帝国の秘境、、」と簡単な英語の説明がある。
日によってはクイズも。翌2日のモロッコ・マラケシュ、イヴ・サンローラン・ミュージアム、彼はコバルトブルーのこの家を1980年代に購入し、2008年に亡くなるまで時折滞在した。さて、サンローランはモロッコ生まれ?正しい/正しくない?(答えは裏面に)という具合だ。
旅に関する引用句が書かれたページもある。
明日はどこだろう?
ページを全部めくり終わるまでに、旅行できますように。
"1,000 Places to See Before You Die"
以前も書いたと思うけど、この本も楽しい。
死ぬまでに見たい1000カ所 ハードカバー第2版
年末小旅行 ― 2020/12/24
旅行なんて書いたけど、何のことはない。60kmほど西の町に1泊しただけだ。
コロナ感染者急増中の東京(駅)を息を潜めて通り抜け、湾の向こうに到着した。主目的はトライアローグ展。横浜美術館では11月から2月末まで開かれている。前日に今年最後の授業を終え、カバン一つでやって来た。

愛知県美術館、富山県美術館と合わせて3館の所蔵品が、時代/テーマ3つのセクションに展示されている。時間予約のため人が少なく、館内は落ち着いていた。
ピカソは1902年の青から60年まで4枚の「女」、マティス、シャガール、ルオーなどは各1枚、油彩転写のクレー3枚。決して平穏ではなかった一年の締めくくりに、カンディンスキーやオキーフと静かに向き合えることを幸運と呼びたい。
共同企画展は撮影禁止だ。横浜コレクションのほうには、デュシャンの大硝子→大鴉になった(ポーではない)らしい吉村益信作品など。こちらもよい。

大して重くもないカバンをホテルに置き、夕方の赤れんが倉庫へ向かった。クリスマスのイルミネーション、きれいですね。周りはほとんどが若い二人連れだ。この近所に住む友だちを誘おうかどうか直前まで迷ったものの、今の状況では迷惑に違いないと見送った。ぐるぐる一人歩き回る中高年。

いつの間にか旅行人格に入れ替わっているようだ。歩く、歩く。早足で中華街まで行き、中国東北料理の小さい店で夕食を取った。羊肉たっぷり、めえ〜。

観光気分で横浜を歩くとしたら、どこへ行くだろう?
翌日はガイドブック通りに建築物三塔巡り、山下公園、氷川丸見学、、
氷川丸の横には移転された白灯台(明治29年設立)があった。塩屋崎からちょうど一年たつけど、今年の灯台には登れません。

さらに歩き、港の見える丘公園から完成間近なガンダムを見下ろし、元町を通って中華街へ戻り遅めのランチ定食。お土産の肉まんを買い、JRに乗って東京を経由し帰宅した。
100年ぶりの災禍に右往左往するばかりだった2020年も残りは1週間、
皆さま、どうぞお体に気をつけて、よいお年を。
三島忌、そして白内障手術 ― 2020/11/25
現代国語の先生がラジオを持って教室に入ってきた。
「大変なことになっている」
今日は三島忌だ。ことさら記憶に残っているのは、誕生日だから?いや、大きな事件が起きた時自分が何をしていたかは、誰でも深く記憶に刻まれるんですよね。ジョン・レノン暗殺や、日航機墜落事故、9.11、東日本大震災、、
今日は雨だが、50年前は小春日和、雲ひとつない晴天だった。阻止しようのない衝撃的な自決、翌日の朝日新聞紙面も思い出せる。
昭和後半の文豪の中で、三島由紀夫はきらびやかに異彩を放っている。とは言え、事件以前に読んでいたのは『潮騒』だけだ。楯の会のことはほとんど知らなかった。
あれから半世紀。瞬く間に、というのは大げさにしても、時間は呆れるほど早く過ぎ、ぼんやりした眼鏡の学生は、曇りガラスのような白内障の中高年になってしまった。
春先から左眼のかすみが気になり始めたかと思ったら、テレワークの影響もあってか症状は急激に進み、7月後半に運転をやめざるを得なくなった。さらに、学校のPCでのZoom画面操作にも不安を覚え、名残惜しいが、夏学期をもって一校を退職した。
白内障手術と言えば、30年以上前に吉行淳之介の『人工水晶体』を読んだことがある。眼内レンズを入れる水晶体再建術は、医療技術の進んだ今ごくありふれた手術だし、日帰り手術も多いようだ。わたしは術後の管理を考え、2泊して標準的な治療を行う近隣の総合病院を選んだ。
母親、ついにサイボーグ化?! と子供たちが騒いだ手術は正味15分ほどで終わった。そして翌日眼帯が取れると、魔法のようにクリアな視界が広がった。
ビームは出せないけど、こうしてあちこち古びた箇所を修理し、できるだけ細く長く生きていくわけですね。ジョン・レノンは40歳で、三島は45歳で亡くなったのだ。馬齢を重ねつつの感慨である。
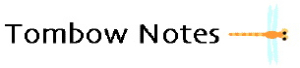





最近のコメント