なるほど、リユース ― 2024/10/22
今年も細々と、オンラインのプライベートレッスンが続いている。
ありがたいことだけど、あらら大変、来週から始まるレッスンは「みんなの日本語初級2」指定だ。困った。しばらく前に、もう使わないだろうと思うテキスト類をごっそり処分してしまったのだ。今さら新品は必要ない。何とか安く手に入れられないものか。
アマゾン、ブックオフのサイトには希望価格のものがない。それで、遅ればせながらメルカリに登録してみた。
始めてみれば便利で、なかなか面白いものですね。
日本語教科書が目的だったのに楽しくなって、ふらふらとPendleton(ネイティヴアメリカン好きなので)を2枚購入し、続いて手持ちのバッグやら服やらを売りに出してしまった。
LLBeanトートバッグ1点お買い上げ!うふふ。
さらに調べてみると、本はアマゾンを通して時々購入しているバリューブックスに、便利な買取サービスがあるらしい。というわけで、現在、部屋の隅に売れるかもしれない/もう読まないかもしれない本が山積みになっている。
リユースはSDGsなのだ。CO2削減なのだ。なんて、いきなり目覚めたらしいけれど、実はまだ教科書を買っていません。どうするんだ。
元気ないけどシアトル(第20次遠征隊#5) ― 2024/10/05
めったにないことだが、フェアバンクス3日目に体調を崩した。嘔吐、発熱、咳、喉の痛み、、旅行人格の空元気も役に立たない。Mが世話してくれたおかげで熱は引いたものの、全く食欲がない。そういう状態の帰り道シアトルだ。楽しいはずのfish toss魚投げパイクプレースも、少し歩けば疲れてしまう。スタバ1号店前の大行列を横目に通り過ぎ、有名チャウダー店に入ったがほとんど味がしなかった。
「ゴールド!ゴールド!ゴールド!」
壁に拡大展示されていたのは、1897年7月蒸気船ポートランド号が2トンの金と68人の大金持ちを乗せてシアトル港に到着した日の新聞見出しだ。富を求める何万人もの人々が、我も我もと北へ向かうことになった。
小さな港町シアトルはそのようにして、19世紀末、金探求者たちが様々な装備品を整える拠点となり急速に発展したという。防寒衣類、頑丈な靴、猟銃、ツルハシ、鍋、小麦粉、ベーコン、砂糖、タバコなどなど、(現在パイオニアスクエアと呼ばれている)商店街の歩道に商品の山がうず高く築かれた。ゴールドラッシュ特需である。解説展示の中に若いジャック・ロンドンの写真を見つけた。

もうひとつのmust-see、シアトル美術館で楽しみにしていたのは、アフリカンアメリカンの画家ジェイコブ・ローレンスの小さな展覧会だった。ハーレム・ルネサンスに学んだ彼の作品は、ひと目見れば印象に残る独特の深い色合いだ。
そしてやはり、ネイティヴ・アートの前でも足が止まる。
Raven 大鴉、ワタリガラス、、ハイダ族では創造性creativityのシンボルとされている。

最終日の夕方、エリオット湾を1時間で小さく一周するクルーズ船に乗った。初秋の風が心地よい。けれど、うつしてしまったのか(ごめんね)旅仲間Mも風邪をひいている。ゴホンゴホンと咳き込む二人。ドラッグストアWalgreensウォルグリーンズで買ったTylenolタイレノールの風邪薬を分け合い帰国した。お疲れさま〜
フェアバンクスで砂金堀り(第20次遠征隊#4) ― 2024/10/04
フェアバンクス3泊の予定を組んだのはオーロラ・ツアーのためだったが、天候に恵まれずキャンセルになってしまった。
他の予定はゴールド・マイニング(砂金堀り)、アラスカ大学北方博物館、ファーマーズ・マーケット、パイオニア・パーク、中心部の街歩き、、のんびりした3日間になった。
アラスカ・ゴールドラッシュという言葉は、たいていの場合クロンダイクでのブーム(Klondike Gold Rush1896-99)を意味している。ジャック・ロンドンのクロンダイクもの(作品)も、今回の旅テーマのひとつだった
ちょっとした体験ができそうだ、と足を運んでみた。
これはgold rush wiki解説のおじさん↓

入り口で20ドルのギャランティ砂金袋を購入する。トレイで水にさらし、石と土を選り分けるやり方を教えてもらう。せっせと作業して残ったのは、数粒の金のフレークだったけど。

その他、備忘用に写真を貼っておこう。
アラスカ大学フェアバンクス校の北方博物館 UA Museum of the North

ここで学んだ星野道夫さんのコーナーがあった。
タナナ・バレー・ファーマーズ・マーケット Tanana Valley Farmers Market に行ってみた。
その土地の人々と話すのが楽しい。フェアバンクスで暮らす日本人にも会った。

さびれたパイオニア・パークの中の小さい博物館に、ロシアからのアラスカ購入(1867年)に関する展示があった。額面720万ドルの小切手↓
金鉱発見はその後のことだ。

フェアバンクスからアンカレジへの帰り道は、アラスカ鉄道で

普通車にも展望車があり、自由に座ることができる。素晴らしい景観の中、川沿いを走るデナリ・スター号 (Denali Star) 午前8時半発、午後8時到着予定だったが、何と3時間の遅延だった、、、。
ワイルドライフ!(第20次遠征隊#3) ― 2024/10/04
デナリ国立公園へはアンカレジから市内1号線を北上し、3号線に合流した後ワシラを経てさらに北へ全約280マイル(380km)、わたしの運転では5時間ほどの距離だ。秋晴れ、ドライブ日和、でも紙の地図しかない。動物的勘がすっかり衰えたわたしは、気がつけば、米軍基地のゲート前にいた。
「デナリに行きたいんですけど」
「全然ちがうよ」(You're absolutely wrong.)
ゲート内で方向を転換し、教えてもらった道路を進むが、ぐるぐる回ったため方角がわからない。さらにガソリンスタンドのおばさんに道順を聞いて、ようやく一本道のパークスハイウェイに出た。鉄道駅のあるタルキートナでホットドッグのランチ、ハイウェイ沿いの紅葉と遠くに見える山々に目を見張りながら、デナリ地区近くのモーテルに辿り着いた。
さて、翌日、デナリ国立公園のツンドラ・ウィルダネス・ツアーバスに乗った。
公園内は一般車乗り入れができないため、人々はツアーに参加するかシャトルバスで広大な公園内を回ることになる。

「ワイルドライフ!」
ゆっくり進むバスの窓から動物を発見した乗客は、そう叫んで、皆と一緒に野生生物を観察するという掟(ルール)があるらしい。運転手とガイドを兼ねたパークレンジャーが、双眼鏡で捉えにくい、遥か遠くの動物も望遠レンズでバス内のモニターに映し出してくれる。

「ワイルドライフ!」
その日見ることができたのは、山の尾根にいた数頭のブラックベアと、切り立った岩山を歩くたくさんのマウテンゴートだった。星野道夫さんの写真で見たムースやカリブーには遭遇しなかった。
それは残念だけれど、何と見事な秋の風景だろう。アラスカに赤く色づくカエデの類はないようだ。
濃い緑の針葉樹の足元一面を赤く覆うのは、ブルーベリーなどの灌木だ。
植村直己さんが消えたままのデナリ山(マッキンリー)は、雲に隠れて見えなかった。
9月に6,190mの全容が見える確率は30%以下だという。
「あの雲の中にあるんですよ」とパークレンジャー、
白く輝く山脈が眺められる地点でバスはUターンした。
ネットなしでアラスカ(第20次遠征隊#2) ― 2024/10/03
9月1日シアトル空港経由でアンカレジに到着。
(乗り継ぎ時、同行者Mがセキュリティの容れ物にスマホを置き忘れ、空港内を走り回ったが)、何とか予定通りレンタカーを借り出した。
スーツケースを乗せ、走り出して青ざめる二人、、、ネットが繋がらない!!
わたしは去年のNZ旅行から、某社のeSimを利用している。以来、アメリカ本土、 モンゴル、中欧、ラオス、タイ、オーストラリア、一度もトラブルなく、現地モバイル通信を利用してきた。つまり、ホテルではwifi、街に出ればモバイルでGoogleその他が使えた。それなのに、一体どうなっているんだ?!
加えて、Mのアメリカ放題(Softbank)も全く繋がらない。二人のiPhoneモバイル表示はSOSだ。SOS、って悪い冗談?
アンカレジ空港の外、Google Mapなしでは西も東もわからない。レンタカー受付で、うっかり紙のマップをもらい忘れている。途方に暮れたが、とにかくホテルに行かなくちゃ。
事前にチェックしておいた町の概略を頭に思い浮かべ、道路表示を確認しながら一方通行の多い中心部をぐるぐる走り、途中別のホテルで道順を尋ねて、およそ2時間後、宿泊予定のホテルを発見した。長い1日だったねえ。
そのアンカレジには2泊。ホテルで入手した紙の地図を頼りに、見応えのある博物館や郊外のモールを回った。QRコードを読み込んで料金を払う市内の駐車場に恐れおののいたり(スマホが機能しません)、ビジターセンターのおばさん職員に助けられたりしながら過ごし、見上げた3日目の虹の写真を置いておこう。夕方のウォルマート駐車場です。
アラスカドライブ、全米50州走破(第20次遠征隊#1) ― 2024/09/27
20回目が最後の遠征隊になった。
アラスカ州をドライブし、これでUSA50州を全部走破したことになる。2005年からほぼ20年かかった。
そして当たり前だけど時間は確実に無慈悲に流れ、50代が70代になりました。
見たいと思い続けていたアラスカの短い秋景色
きっかけは、以前にも書いたが、詩人長田弘さんの『アメリカの61の風景』だ。長田さんは片道1車線の地方道を10万マイルゆっくりとドライブしたそうだが、わたしは気忙しくインターステートも走ってテリトリーを広げた。ほんの1マイル入っただけでUターンした州もある。ごめんね、アイダホとロードアイランド。
(まだ遠征隊という呼称なしの)第1次カリフォルニアでは、「走り方が遅過ぎる!」とパトカーに呼び止められたこともあったっけ。
友人たちに呆れられるが、左右を取り違えることもしばしば(左利きのせいにしているけど、本当はどこか足りないのだと思う)。よくぞ無事に50州走ったものだ。
とりあえず、完走おめでとう、自分。
ニューヨークタイムズ「読者が選ぶ21世紀の100冊」 ― 2024/08/20
少し前だが、ニューヨークタイムズに
「読者が選ぶ21世紀の100冊」という記事が載っていた。

そこからリンクする The 100 Best Books of the 21st Century (こちらは文学関係者数百人が選んだベスト10アンケートをブックレビュー部が集計)のほうには、読んだ/読みたいのチェック欄もあって、短い解説も面白い。
両方にざっと目を通したら、今までに14冊ほど読んでいた。
もちろん翻訳でね。
2つのリストにはズレもあり、カズオ・イシグロ、コルソン・ホワイトベッド、イアン・マキューアンはどちらにも選ばれているが、スティーヴン・キング、村上春樹、パティ・スミスはブックレビュー部のベスト100に見当たらないし、リディア・デイヴィスとルシア・ベルリンは読者のベスト100には入っていない。そして、あれれ、ポール・オースターはどこに? ふーむ。
ところで、『ウルフホール』と『ザリガニの鳴くところ』は、映画を見ただけかもしれない。
『ライフ・オブ・パイ』は本も読んだんだっけ?
どちらもわくわくするようなリストではあります。
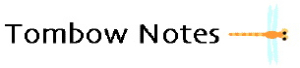












最近のコメント