最後の川村記念美術館 ― 2025/03/15
何回かの訪問で最も印象に残っているのは、階段を上がると広がる明るい部屋に架けられたバーネット・ニューマンの大作「アンナの光」だ(縦276cm 横611cm)。
2013年に売却されて、もう見ることはできない。探してみたら、紋谷幹雄さんという方のサイトに画像を見つけましたので、お借りします。https://monyaart.jugem.jp/?eid=3570

はじめてこの絵と向かい合った時、静かに座っている係の女性に
「1日中、これを見ているんですね。何を考えますか」と尋ねると
「アンナというのはバーネット・ニューマンのお母さんです。
わたしも母を亡くしているので、いろいろ思い出しています」
というお返事をいただいたことを思い出す。
2011年にはヘンリー・ムーアのある広場に、4種類のひまわりが植えられていたことも印象深い。
ゴッホ、ゴーギャン、マチス、モネのひまわりが咲き誇る!と聞いて、夏の初めに行ってみたら、ゴッホのひまわりがひとつだけぽつんと、背を伸ばして咲いていたっけ。

やっぱりもう一度行かなきゃ、と車を走らせたのは3月初旬の冷たい雨の日だった。閉館間近の美術館は、悪天候にも関わらず人が多かった。ざわざわしたロスコの部屋に座って、今まで通りしばらく時間を過ごした。美術館前の池では白鳥が2羽、噴水の先の岸辺でじっと動かなかった。さよなら、さよなら、もう来ないの。
六本木に新設される美術館にもRothko Roomができるというニュースはうれしいけれど、何と作品の3/4は売却されてしまうらしい。シャガール「ダビデ王の夢」やカンディンスキー、エルンスト、ポロックにまた会えるといいんだけど。
ヘミングウェイはシンガポールへ行かなかった ― 2025/02/27
ほぼ半世紀ぶりのシンガポールだった。
遠い昔とも言える1970年代のシンガポールに、マーライオンはいなかった。
記憶しているのは、蘭の花が美しい植物園、タイガーバーム・ガーデンという公園、そしてラッフルズホテルだ。地下鉄はなく、ポツンポツンとホテルの並ぶ広いオーチャードロードを自転車タクシー、トライショーで移動したことを覚えている。それはシンガポールがマレーシアから独立した1965年から10年余り後のことなのだ。
今や、超近代都市となったシンガポール。クラークキーからのリバークルーズ、マリーナベイ地区の(チームラボ)アート・サイエンスミュージアムやガーデンズ・バイ・ザ・ベイ、対岸の大観覧車シンガポール・フライヤー、ナイトサファリ、リトル・インディアやアラブ人街などで、忙しく4日間を過ごした。
それから、フェリーで1時間足らずのインドネシア領ビンタン島へ渡って4日間。活動的な前半とは対照的にプールサイドでゆっくり本を読んだ。予想以上に無惨に日焼けしてしまったけれど、よい休日だった。
という旅記録を書くため昔のシンガポールについて調べていたら、気になる記事をいくつも発見した。シンガポール・スリング発祥の地であるラッフルズホテルは、ヘミングウェイが宿泊したことで有名だ、というのだ。
えっ?ヘミングウェイがシンガポールに?
何かの間違いでしょう。それとも、わたしが知らなかっただけ?

Hemingway Adventure by Michael Palin
モンティ・パイソンの人気者、知性派のイギリス人コメディアン/作家マイケル・ペイリンは、ヘミングウェイの大ファンだった。BBCで『ヘミングウェイ・アドベンチャー』というシリーズを制作し、またヘミングウェイが訪れた世界各地への旅記録の本(上記)も出している。
わたしのヘミングウェイ・アドベンチャーは、この本を大いに参考にしていた。ペイリンの助けで、シカゴ近郊のオークパーク(ヘミングウェイの生家)や、パリのアパート、キーウエスト、キューバのハバナへ行った。また、ヘミングウェイで有名なマドリッドのレストラン子豚の丸焼きボティンや、ヴェネチアのハリーズバーにも出かけてみた。キリマンジャロは遠すぎるけれど、ヘミングウェイゆかりの地には、ずいぶん熱心に足を運んだものだ。
でも、彼がアジアの国に?シンガポールに?
ペイリンだって一行も書いていないよね。
嘘でしょう、、?
ChatGPTに聞いてみよう。
答えはすぐに出た。
ヘミングウェイがシンガポールを訪れたという記録は確認されていません。
アジアへの訪問については、中国(重慶など)や香港には行った記録がありますが、
シンガポールについての言及は見つかりません。
ほらね(ちょっと得意そう)。
ヘミングウェイより少し前の世代の作家たち、サマセット・モームやコンラッドなどはラッフルズホテルやバンコクのオリエンタルホテルに(長期)滞在したという。
この混乱の理由のひとつは、思うに、カクテルのシンガポール・スリングが、ハバナのパパ(ヘミングウェイ)のフローズン・ダイキリやモヒートと同じように、文学の香りを帯びた飲み物だという共通点にもあるのだろう。
いつもの週末、いつもの図書館 ― 2025/01/12
年末年始の(楽しい)イレギュラー期間が終わって、普通の日曜日が戻ってきた。
降っても晴れても、雨でも風でも、日曜は午前中に隅々まで掃除機をかける(シニア夫婦はそれぞれのテリトリーを分担)。必要に応じて(夫には指令を出して)拭き掃除も行う。
(これは毎日のことだが)お洗濯物を干し、電動ミルで豆を挽いてドリップで800mlくらいのポットにたっぷりコーヒーを入れる。
野菜ジュース、チアシードを加えておいたヨーグルト+黒豆とナッツ+ハチミツ、コーヒーで軽い朝食を摂りながら(現在あまり効果の上がらないダイエット中)、テレビはTBSサンデーモーニングを見る。
夕方、3ブロック先の図書館分室に行き、いつも帰りに八百屋さんに立ち寄る。
今日は年末から借りていた『世界のアーティスト250人の部屋』 副題:人生と芸術が出会う場所 というすてきな本を返却し、届いていた『ソーンダーズ先生の小説教室』と 旅行ガイドブック2冊を受け取った。

小説教室は560ページと分厚い本で、まだ「はじめに」の数ページに目を通したところだけど、
スタインベックに出会った頃の若いソーンダーズはトム・ジョードと同じようにくたびれ果てており、小説がもたらすのっぴきならない世界の感じが、一見静かで内向きで非政治的な(実は絶え間ない検閲の恐怖のもとで書かれた)ロシア小説と共通の作用を持つのだから、
作品を読めばそれまでの自分ではいられないような読書体験を通して、
この劣化した現代をわたしたちはどのようにやり過ごせばいいのか、なにを為すべきなのか、どうすれば平穏を得られるのか、どうして喜びを感じて生きられるのか、
という言わばロシア的な大疑問を(小説を読む時に働く頭の部分は、世界を読む時に働く部分でもあるので)考え続けるための助けになる本のようだ。
12月のペナン5日間 ― 2025/01/07
ペナン旅行の計画を立て始めた時、必ずしようと思っていたことがある。マレーシア・ラクサを食べること、17年前に教えたK君に会うこと。
K君のいた2007年の初級クラスは少人数で学生が確か10人、旧校舎の教室は小さく、エアコンの代わりに冷風扇が置いてあった。
会話の練習で人数が足りない時には、その冷風扇、愛称「エアコン君」が誰かとペアになり、シュールなオリジナル会話を作ったりする楽しいクラスだった。
今、教室記録の写真を探し出してみると、R2D2っぽいエアコン君を取り囲むようにして、様々な国からの学生たちが笑っている。
そのクラスにいたとりわけ愉快で心優しい青年がペナン出身のK君で、フェイスブック上のつながりがずっと続いており、ペナンに行くなら絶対に会わなくちゃ、と思っていたのだ。
けれど、旅行の連絡をする直前に、K君は亡くなっていた。
なんて悲しい残念なことだろう。
弟さんよると、とても進行の早いガンだったという。お願いして、お墓参りをさせていただいた。
そんな12月のペナン5泊だが、幼なじみMとの旅行に娘も合流して、街歩きはわいわいにぎやかだった。写真を何枚か置いておこう。
島の北部、海沿いのホテルに宿泊した。アプリGrabで車を呼び、ジョージタウン市内やナイトマーケットに移動。時間がゆっくり流れていた。
プラナカン・マンション 絢爛豪華な邸宅

世界遺産の旧市街には、数多くのストリートアートがある。
美しいブルーマンションは、中国出身の実業家が19世紀末に建てた家だ。
もちろん行きましたとも、ラクサの有名店 うまい!

Jettyと呼ばれる水上集合住居の壁にもアートがあった。
久しぶりに丸善で本を買う ― 2024/11/18
週末、友人と丸の内ランチの後、オアゾの丸善に立ち寄った。
そして、とても久しぶりに岩波文庫を2冊購入した。
トニ・モリソン『暗闇に戯れて 白さと文学的想像力』
ジョン・スタインベック『チャーリーとの旅 アメリカを探して』

ここ何年も、新聞の書評や広告などで気になった本を図書館にリクエストし、さんざん待たされた末に読んで、これは手元に置きたいと思うものだけAmazonなどで(中古本を)購入している。その方法なら増える本は年に20冊ほど。ものを増やしたくない年齢には程よいペースだと思う。
けれど、ごくまれにリアル書店に足を運んでみると、知らずにいた本がずらりと並び何とも刺激的だ。海外文学コーナーで『ソーンダーズ先生の小説教室』を発見した。ロシア文学の講義らしい。ソーンダーズはシラキューズ大学の教授でもある。ん、そう言えば、シラキューズって、ルー・リードが詩を学んだ大学じゃない?その場で図書館にネット予約した。
ルシア・ベルリン新刊の短編を一篇立ち読みする。これはもう、すぐにでも手に入れたい。娘からの誕生日祝いにちゃっかりリクエストしよう。
上の階に上がると、今年亡くなった松岡正剛さんの「松丸本舗」についての説明が掲示されていた。あのめくるめく本の森があったのは、2009年からのたった3年間だったのか。
それから広い文庫本コーナーの棚の間をゆっくり歩いた。
トニ・モリソンの強く美しい表情に目を奪われる。
サイマル出版版とポプラ社版(どちらも図書館の本)で2回読んだスタインベックのロードトリップ記録は、しばらく絶版になっていた。青山南さん新訳は出版されたばかりのようだ。
レジでオアゾ20周年記念のカバーをかけてくれた。開店したばかりの頃は仕事帰りに時々立ち寄り、洋書売り場の椅子に座って(高過ぎて買えない)写真集や美術書を広げたものだ。
世間が面白くない時は勉強 その2 ― 2024/11/11
8年前のアメリカ大統領選でヒラリー・クリントンが敗れた時、
「世間が面白くない時は勉強にかぎる」という言葉があるそうだ(半歩遅れの読書術、國府功一郎、日経新聞10月16日)と書いたことを思い出した。
あの時、落胆しながら、
頭脳明晰で比類ない経験を持つ女性、面白みに欠けるかもしれないが、公平で度量の大きなヒューマニストだと思う。そういう女性が次に登場するまでに何年かかるのだろう。
と憂いたけれど、そう長くはない時間を経て現れたのがカマラ・ハリスだった。
理解しかねるアメリカの選択だ。世間は全くもって面白くない。この脱力感を何で埋めよう。
という理由からかどうか、自分でもわからないが、
最近久しぶりに読んでいるイギリス文学が、これまでになく面白い。
ヴァージニア・ウルフ『燈台へ』、故ポール・オースターが言った通り、よい作品だった。
イアン・マキューアン『贖罪』、映画だけではない。怖いくらいの素晴らしさ。
そしてジェイン・オースティン『自負と偏見』、細部がなかなか愉快な話なのだ。
リユース、その後 ― 2024/11/03
Vブックス宛に3箱、本をぎっしり詰めて送ったのが1週間前。
数日で査定結果のメールが送られてきた。外出中だったため、ざっと読んでOKしてしまったが、その後リストに載っていない本がずいぶんあることに気づき、問い合わせてみた。
データベースに存在せず買い取れなかった商品や
査定対象外の商品は明細に記載できかねている、とのこと。
ふーん、そうなんだ。
確かにかなり古い本(筑摩書房の太宰治全集とか)を入れたし、仕方ないとは思ったが、
査定額0で記載された新潮クレスト・ブックスが、サイトのトップページから検索してみると、買取り参考価格399円と表示されている。ジュンパ・ラヒリ作品を含むクレスト・ブックスは、どれも良い状態で本棚に並べておいたはず。
どういうことなのかな。
リユースで大きなお金が入ってくるとは考えていなかったが、足を踏み入れてみると、いろいろ釈然としないことが起きるようだ。
実は、本の整理と同時に、タンスに眠っていた着物の買取り依頼も始めてみた。現在、評判のよい3社に絞った出張査定が終わったところなのだが、これがさらに、違和感だらけの納得いかない腑に落ちない割り切れない状況なのだ。噂には聞いていたけど。
今や高齢者となった昭和の娘たちのタンスには、たくさんの(かつて高価だった)美しい着物が大切にしまわれているわけで、同年代の友人たち数人に今回の査定結果を知らせることになっている。みんなびっくり!がっかり!だろうなあ。
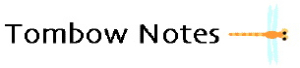











最近のコメント